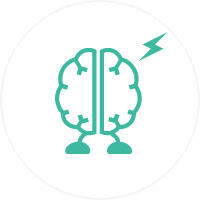化学実験、バイオ実験のノウハウなど、毎日の実験・分析に役立つ情報をお届け。

前回の記事では、アルカリ-SDS法によるプラスミド溶液の調製法の実験手順について解説しました。
続編の今回は、原理について解説します。
プラスミドDNA精製法の原理
前回ご紹介した精製法では、プラスミドを増幅する宿主に大腸菌を使います。アルカリ-SDS法で大腸菌を溶菌すると、目的のプラスミドDNAと一緒に大腸菌のゲノムDNAやRNA、タンパク質や脂質なども溶出されます。これらの不純物は、精製のどのステップでどのように除かれるのでしょうか?その原理を知ることは、不純物の量をできるだけ減らしながら、プラスミドを十分に回収するためにとても大切になります。
1.アルカリ-SDS法によるプラスミド粗抽出液の調製
大腸菌を溶菌してプラスミド溶液を得るときには、プラスミドDNAをできるだけ多く回収することに加えて、そこに含まれる不純物をできるだけ少なくする必要があります。アルカリ-SDS法の「再懸濁→溶菌(アルカリ-SDS変性)→中和」のプロセスで、菌体成分のタンパク質や脂質などは溶菌と同時に変性し、中和により沈殿物となるので、プラスミドDNAを含む溶液(粗抽出液)と分けることができます。
その他の不純物である大腸菌のゲノムDNAはプラスミドと同じくDNAであるため、プラスミドと分けることは容易ではありません。いったいどのようにして、プラスミドDNAとゲノムDNAを選り分けるのでしょうか?プラスミドや大腸菌ゲノムはともに2本鎖の環状DNAで、アルカリ処理(溶菌)によって1本鎖に解離します。このとき、ゲノムDNAは分子量が大きく、DNA鎖に切れ目(ニック)が入りやすいため、解離した1本鎖は直鎖状へと形が変わり、相補鎖が互いに離れてしまいます。一方、分子量が比較的小さく、スーパーコイル状のプラスミドDNAは、もつれた知恵の輪のように、解離した相補鎖が互いに離れずにとどまります。この状態でアルカリ処理を中和すると、プラスミドDNAは互いに近傍にある相補鎖が容易に再会合(2本鎖形成)し、溶液(粗抽出液)として回収されます。対照的に、互いに離ればなれになったゲノムDNA相補鎖(1本鎖)は、容易に再会合できずにタンパク質など(沈殿物)と凝集し、溶液中から除かれます。[参照: プラスミドDNAの電気泳動3]
2.粗抽出液から高純度のプラスミド溶液を調製するために
アルカリ-SDS法で得た粗抽出液には、多くの場合、除去しきれなかったタンパク質やRNAなどの不純物が含まれています。より高純度のプラスミド溶液を得るためには、精製操作を追加する必要があります。
もっとも基本的なものとして、プラスミドDNA(高分子コロイド)を塩とアルコールの存在下で凝集・沈殿させる「コロイドの塩析(アルコール沈殿)」が知られ、DNAの塩析条件で可溶する不純物をプラスミドDNAと分けることができます。中でも、工タノールを用いた塩析(エタノール沈殿)はもっとも一般的ですが、DNAと化学的性質がよく似たRNAも共沈殿してしまう点に注意が必要です。プラスミドへのRNAの混入をできるだけ除くためには、RNAの共沈殿がほとんど生じないポリエチレングリコール(PEG)を用いた塩析(PEG沈殿)が行われます。また、混入するRNAへの対処として、粗抽出液(再懸濁バッファー)中にRNA分解酵素(RNase A)を添加してRNAを分解する方法も有効です。
粗抽出液に残るタンパク質を除くために、フェノ・クロ混液を用いた「フェノール・クロロホルム抽出(除タンパク質操作)」が行なわれます。粗抽出液をフェノ・クロ混液(pH 8.0)と混ぜて遠心分離すると、タンパク質が変性し、水層と油層の界面(中間層)で不溶化するため、水層に溶解するDNA(やRNA)と分けることができます。アルコール沈殿では、核酸とともにタンパク質も沈殿することが多いため、アルコール沈殿の前にフェノール・クロロホルム抽出を行うことで、混入タンパク質が除かれた純度の高いプラスミド溶液が得られます。また、この除タンパク質操作は、粗抽出液に添加したRNase Aの活性の大部分を失活させ、水層から除くこともできます。
ここでご紹介した精製法では、制限酵素を用いたDNAクローニングやDNAシークエンス解析またはPCRなどに直接用いることができる比較的純度の高いDNA溶液を調製することができます。調製したプラスミド溶液の一部をアガロースゲルで電気泳動すると、プラスミドの鎖長・分子のかたち(フォームI/II/III)・大まかな濃度やRNAの混入量を確認することができます[参照: プラスミドDNAの電気泳動]。一方で、培養細胞へのトランスフェクション(遺伝子導入)実験などに使用する場合には、陰イオン交換クロマトグラフィーなどの精製操作をさらに加えて、大腸菌由来の内毒素(エンドトキシン)を除去することが推奨されます。
この記事は、理系研究職の方のキャリア支援を行うパーソルテンプスタッフ研究開発事業本部(Chall-edge/チャレッジ)がお届けする、実験ノウハウシリーズです。
*監修
パーソルテンプスタッフ株式会社
研究開発事業本部(Chall-edge/チャレッジ)
研修講師(理学博士)
関連記事Recommend
-

細胞の免疫蛍光染色 実践編(2/2)
リケラボ実験レシピシリーズ
-

細胞の免疫蛍光染色 基本編(1/2)
リケラボ実験レシピシリーズ
-

細胞内でRNA干渉を人為的に誘導するために RNA干渉による遺伝子発現の調節(2/2)
リケラボ実験レシピシリーズ
-

RNA干渉(RNA interfering, RNAi)とは? RNA干渉による遺伝子発現の調節(1/2)
リケラボ実験レシピシリーズ
-

免疫沈降法(Immunoprecipitation)による目的タンパク質の濃縮 基本から応用まで
リケラボ実験レシピシリーズ
-

ウェスタンブロットによるタンパク質の発現解析(3/3)ウェスタンブロットによるタンパク質の検出
リケラボ実験レシピシリーズ
-

ウェスタンブロットによるタンパク質の発現解析(2/3)培養細胞抽出液のSDSポリアクリルアミド電気泳動
リケラボ実験レシピシリーズ
-

ウェスタンブロットによるタンパク質の発現解析(1/3)タンパク質実験をはじめるための基礎知識
リケラボ実験レシピシリーズ
-

リポフェクション法による遺伝子導入のプロトコル
リケラボ実験レシピシリーズ トランスフェクション(2/2)
-

遺伝子導入技術 トランスフェクションの基礎知識
リケラボ実験レシピシリーズ トランスフェクション(1/2)